
自転車レッドカードとは何ですか?と疑問に思う方もいるでしょう。このカードは、罰金がないから意味ない、何枚までもらえるなら捨てるとどうなるのか、と軽く考えられがちです。しかし、特に中学生や高校生が3枚もらうような事態になると、その影響は無視できません。この記事では、自転車指導警告カード、通称レッドカードと、より重い処分である赤切符との違いを明確にし、交通違反を犯した際にどうなるのかを徹底解説します。
- 自転車レッドカードの法的な意味と目的
- 違反を繰り返した場合の具体的な罰則
- 中学生や高校生など未成年者への影響
- 赤切符との違いと前科のリスク
自転車レッドカードの基本知識とルール
- 自転車のレッドカードとは何ですか?
- レッドカードは本当に意味ないのか?
- もらったカードを捨てるとどうなる?
- レッドカードは何枚までもらえるの?
- レッドカードが3枚になると起こること
自転車のレッドカードとは何ですか?
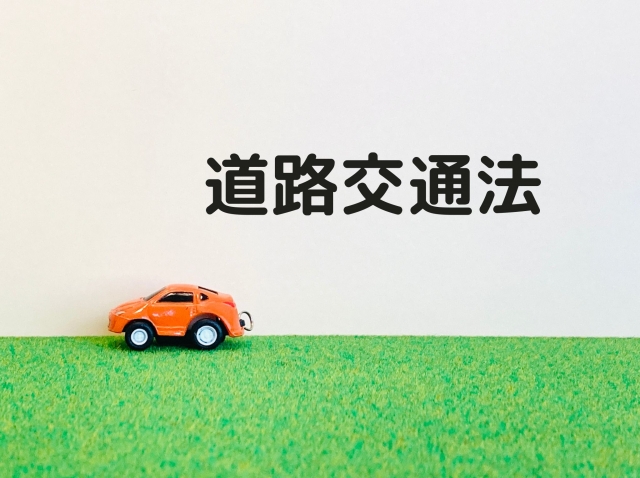
自転車のレッドカードとは、正式には「自転車指導警告カード」と呼ばれるもので、警察官が自転車の危険な運転や交通違反に対して交付する警告票のことです。これは法律に基づく刑事罰や行政罰ではなく、あくまで運転者に対して交通ルールの遵守を促し、将来の事故を未然に防ぐことを目的とした「指導・警告」の一環になります。
道路交通法において、自転車は「軽車両」として明確に位置づけられており、自動車やオートバイと同じく交通法規を守る義務があります。しかし、運転免許が不要である手軽さから、そのルールへの意識が低い運転者も少なくありません。そこで警察は、比較的軽微な違反行為に対し、いきなり罰金や刑事手続きといった重い処分を下すのではなく、まずはこのカードを用いて注意喚起を行うという段階的な対応を取っているのです。
交付対象となる主な違反行為の例
- 信号無視(道路交通法第7条違反)
- 一時不停止(同法第43条違反)
- 二人乗り(同法第57条2項違反)
- 夜間の無灯火運転(同法第52条違反)
- 傘差し運転(各都道府県の公安委員会規則違反)
- スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」(同規則違反)
- イヤホンやヘッドホンで周囲の音が聞こえない状態での運転(同規則違反)
これらの違反行為が確認された際に、警察官の判断で口頭での注意に加えて、あるいは再発防止を強く促すためにこのカードが手渡されます。地域によっては「イエローカード」という名称で運用されている場合もありますが、その目的と効力は基本的に同じものです。
「自分は歩行者の延長」という感覚は捨て、自転車は「車両」であるという意識を持つことが、レッドカードを受けないための第一歩です。
レッドカードは本当に意味ないのか?
「レッドカードをもらっても罰金はないし、意味ないのでは?」という声は確かによく聞かれます。実際に、カードを交付されたこと自体で直ちに罰則が科されたり、前科がついたりすることはありません。この点が、カードの効果を疑問視する声につながっているのでしょう。
しかし、「意味ない」と考えるのは非常に危険です。このカードは、目に見えるペナルティ以上に重要な意味を持っています。
自転車レッドカードが持つ本当の意味
警察は、誰に、いつ、どのような違反でカードを交付したかという情報を記録・保存しています。この記録は、運転免許の点数のように累積するものではありませんが、次に同じ運転者が違反を犯した際の対応を判断するための重要な資料となります。つまり、一度でも警告を受けたという事実が公式な記録として残るのです。
この記録があることで、警察は違反を繰り返す運転者を「危険な運転の常習者」として認識できます。その結果、次に同様の違反で取り締まりを受けた際には、単なる警告では済まされず、より厳しい処分である「赤切符」の交付に繋がる可能性が格段に高まります。したがって、レッドカードは「これが最後の警告ですよ」という強いメッセージであり、自身の運転を見直すための重要な機会と捉えるべきです。
もらったカードを捨てるとどうなる?

警察官から手渡された自転車レッドカードを、その場で、あるいは後で捨てるとどうなるのでしょうか。結論から言うと、カードを捨てる行為自体が何らかの罪に問われることはありません。
レッドカードは、あくまで運転者本人に警告の意図を伝え、今後の安全運転を促すための紙片です。所有権は受け取った本人に移るため、それを保管するか処分するかは個人の自由になります。そのため、捨てたことが発覚して罰せられるようなことはないでしょう。
重要なのはカードの有無ではなく「記録」
前述の通り、大切なのはカードという「物」ではなく、警察のデータベースに残る「警告を受けた記録」です。カードを捨てて手元からなくしたとしても、違反の記録が消えるわけでは決してありません。警察のシステムには、あなたの氏名や住所、違反内容がしっかりと記録されています。
したがって、カードを捨てる行為は問題ありませんが、「警告された事実は公式記録として残っている」という事実を忘れてはいけません。警告を真摯に受け止め、記載された違反内容を再確認し、自身の運転習慣を見直すきっかけとすることが、このカードの本来の目的なのです。
レッドカードは何枚までもらえるの?
自転車レッドカードには、「何枚まで」という明確な上限は設けられていません。運転免許の違反点数制度のように、「合計で〇点に達したら免許停止」といった具体的な基準が存在しないためです。理論上は、違反をするたびに何度も交付される可能性はあります。
しかし、これはあくまで制度上の話です。実際には、複数回にわたってカードを交付される状況は極めて危険なサインと捉えるべきでしょう。警察は違反記録を蓄積しており、2回、3回と警告が重なれば、その運転者は「警告を無視して危険運転を繰り返す悪質な人物」としてマークされることになります。
警察も、何度も同じ人に警告だけを続けるわけではありません。警告で改善が見られないと判断されれば、より厳しい措置、つまり刑事手続きを伴う「赤切符」での検挙へと移行するのが自然な流れです。何枚ももらえるから大丈夫、という考えは絶対に持つべきではありません。
また、信号無視などの特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講対象となります。これはレッドカードの枚数とは直接関係ありませんが、警告を受けるような運転を続けていれば、講習対象となる可能性も高まります。レッドカードに上限はないものの、実質的には「次はない」という警告です。一枚もらったら、それを最後の警告と捉え、二度と交通違反を犯さないように運転習慣を改めることが重要になります。
レッドカードが3枚になると起こること
レッドカードに明確な枚数の上限はないと述べましたが、俗に「3枚たまると大変なことになる」と言われることがあります。これは法的な規定ではありませんが、度重なる警告の結果として起こりうる事態を指しており、あながち間違いではありません。
レッドカードを2回、そして3回と立て続けに交付されるような状況は、警察から「指導・警告では改善の見込みがない危険な運転者」と見なされることを意味します。その結果として起こりうること、それは赤切符による検挙です。
軽微な違反であれば通常は警告で済みますが、短期間に3回も同じような違反を繰り返すとなれば話は別です。警察官は、その悪質性・常習性を重く見て、次は警告ではなく、刑事罰の対象となる赤切符を交付するという判断を下す可能性が非常に高くなります。
3枚の警告が意味すること
- 警察からの信頼を失い「要注意人物」としてリストアップされる
- 次回の違反時には、警告なしで即座に赤切符を切られる可能性が高まる
- 自転車運転者講習の対象となるリスクが現実味を帯びてくる
このように、「3枚」という数字自体に法的な効力はなくとも、違反の常習性を示す重要な目安となります。1枚、2枚と警告を受けた段階で、自身の運転の危険性を真摯に反省し、行動を改めなければ、3回目には取り返しのつかない事態に発展しかねないと心得るべきです。
自転車レッドカードの罰則と対象者への影響
- レッドカードで罰金は発生するのか
- 重い処分である赤切符との違いとは
- 中学生がもらった場合の影響について
- 高校生は学校に連絡されるのか?
- 自転車レッドカードを理解し安全運転を
レッドカードで罰金は発生するのか

結論として、自転車レッドカード(自転車指導警告カード)を交付されたこと自体で、直接的に罰金が発生することはありません。このカードはあくまで行政指導の一環であり、刑事罰や行政罰である罰金や反則金とは法的な性質が全く異なります。
そのため、警察官からカードを手渡された際に、その場で金銭の支払いを求められることは一切ありません。この「直接的な金銭負担がない」という点が、一部で「レッドカードは意味ない」と誤解される最大の理由でしょう。
しかし、将来的に罰金につながる可能性は十分にあります。レッドカードによる警告を無視し、危険な運転を繰り返した結果、次に「赤切符」を交付された場合は話が大きく変わります。赤切符は刑事手続きへの移行を意味するため、検察官による起訴を経て裁判で有罪となれば、「罰金刑」という形で金銭を支払う義務が生じるのです。
罰金と反則金の違い
自動車の軽微な違反で支払う「反則金」は行政罰であり前科にはなりませんが、赤切符を経て科される「罰金」は刑事罰であり、前科がつくことになります。レッドカードは、この重い処分への入り口になりうる警告なのです。
さらに、3年以内に信号無視などの危険行為を2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。この受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されるため、間接的に罰金につながるケースもあると言えるでしょう。
重い処分である赤切符との違いとは
自転車の交通違反における「レッドカード」と「赤切符」は、その意味合いと法的な重さが全く異なります。両者の違いを正しく理解することは、安全運転を心掛ける上で非常に重要です。
レッドカードが指導・警告に留まるのに対し、赤切符(正式名称:告知票)は刑事手続きの開始を意味するものであり、その後の対応が大きく変わってきます。悪質な違反や、警告を無視して違反を繰り返す運転者に対して交付されます。
| 種類 | 通称 | 目的 | 法的効力 | その後の展開 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車指導警告カード | レッドカード、イエローカード | 交通ルールの指導・警告 | なし(警察内の記録のみ) | 改善が見られなければ次回以降の処分が重くなる |
| 交通切符(告知票) | 赤切符 | 刑事事件としての検挙 | あり(刑事手続きの開始) | 検察庁への送致、起訴されれば刑事裁判となり、罰金刑や懲役刑の可能性(前科が付く) |
| 交通反則告知書(2026年導入予定) | 青切符 | 反則金の納付による 刑事手続きの免除 |
あり(行政罰) | 反則金を納付すれば手続き終了(前科は付かない)。未納の場合は刑事手続きへ移行。 |
このように、レッドカードは「まだ引き返せる警告段階」、赤切符は「刑事事件として扱われる段階」と、両者には天と地ほどの差があります。赤切符を交付されると、罰金刑であっても前科がつき、将来の就職や資格取得に影響が出る可能性も否定できません。警察庁のウェブサイトでも繰り返し啓発されているように、自転車は車両であるという意識を常に持つことが大切です。
中学生がもらった場合の影響について
中学生が自転車で交通違反を犯し、レッドカードを交付された場合、大人とは少し異なる対応が取られることがあります。これは懲罰よりも教育的な指導を重視するためです。
まず、自転車指導警告カードの交付対象は原則として14歳以上とされています。日本の刑法では14歳未満は刑事責任を問われないため、それに準じた運用となっています。そのため、中学2年生以上であれば、大人と同様にカードを交付され、警察に違反記録が残ります。
中学生の場合、特に重視されるのが保護者や学校との連携です。警察が違反の状況や本人の反省度合いを見て、必要だと判断した場合には、保護者へ連絡が入ったり、中学校へ情報提供されたりすることがあります。これにより、家庭と学校が連携して交通安全指導を行うことを促す目的があります。
14歳未満(中学1年生の一部など)の場合
刑事責任を問われない14歳未満の子供が危険な違反をした場合、レッドカードの交付ではなく、その場で指導が行われます。警察、学校、地域で個人を特定しない形で情報が共有され、今後の交通安全教育に活かされることがあります。
中学生にとって、警察から直接指導を受け、その事実が学校や親に知られることは精神的に大きな出来事です。これを単なる「叱られた経験」で終わらせず、交通ルールの大切さを学び、安全な運転を身につける良い機会と捉えることが大切になります。
高校生は学校に連絡されるのか?

高校生が自転車レッドカードを交付された場合、学校に連絡される可能性は十分にあります。中学生の場合と同様に、警察は未成年者の健全育成の観点から、学校と連携して指導を行う方針を取っているためです。
特に、以下のようなケースでは学校へ連絡が行く可能性が高まります。
- 通学中の違反であった場合
- 制服を着用しており、所属高校が明らかである場合
- 違反が悪質、または危険性が高いと判断された場合
警察から学校へ連絡があると、学校は生徒指導の一環として、本人および保護者に対して交通安全に関する指導を行います。学校によっては、校則に基づいた特別な指導や、反省文の提出、奉仕活動などが課される場合もあるでしょう。
進路への影響は?
レッドカードをもらったこと自体が、直ちに内申書に記載されて大学受験や就職に不利になることは通常ありません。しかし、違反が悪質であったり、何度も繰り返したりして「赤切符」を切られるような事態になれば、それは刑事手続きであり、状況によっては学校から停学などの厳しい処分が下される可能性も否定できません。そうなれば、進路に影響が及ぶことも考えられます。
国土交通省が公開している資料では、高校生が起こした自転車事故で約9,266万円という高額な賠償命令が出た事例も紹介されています。「たかが自転車」という軽い気持ちが、人生を左右する大きな問題に発展するリスクがあることを、高校生自身が深く理解する必要があります。
自転車レッドカードを理解し安全運転を
- 自転車レッドカードは法的な罰則がない指導・警告のカード
- 罰金はないが警察に違反の記録が残る
- 意味ないと軽視すると赤切符など重い処分につながる
- カードを捨てても違反記録は消えない
- 何枚までという上限はないが2回目以降は危険信号
- 3枚もらうと赤切符を切られる可能性が非常に高まる
- 赤切符は刑事罰であり罰金刑や前科がつく可能性がある
- 2026年からは16歳以上を対象に青切符制度が導入される
- 中学生(14歳以上)もレッドカードの交付対象となる
- 違反をすると保護者や学校に連絡が行くことがある
- 高校生が通学中などに違反すると学校に連絡される可能性が高い
- 違反の繰り返しは内申や進路に影響するリスクもゼロではない
- 自転車は道路交通法上の「軽車両」である
- 警告を真摯に受け止め運転習慣を見直すことが重要
- 安全運転は自分と他者の命を守るために不可欠





